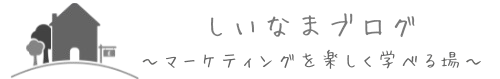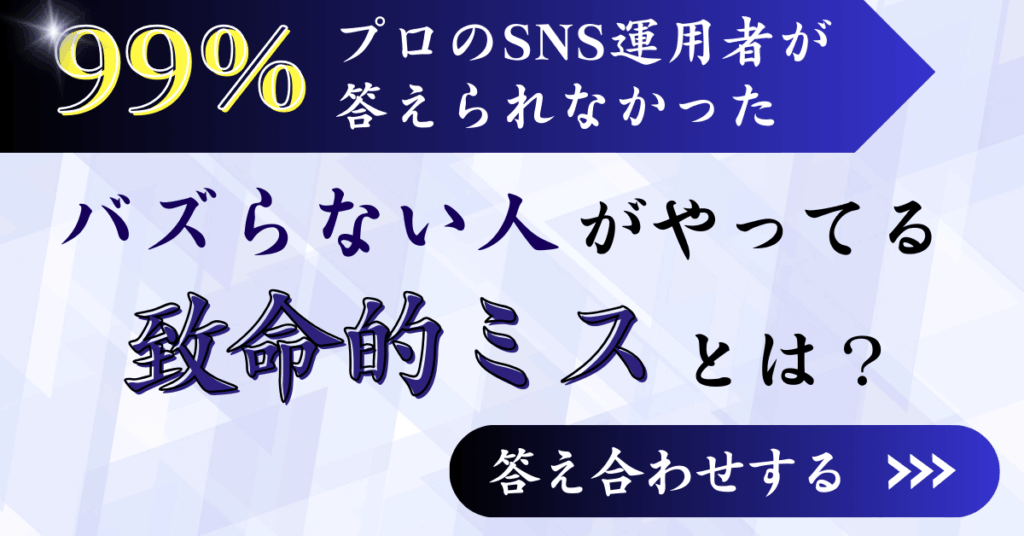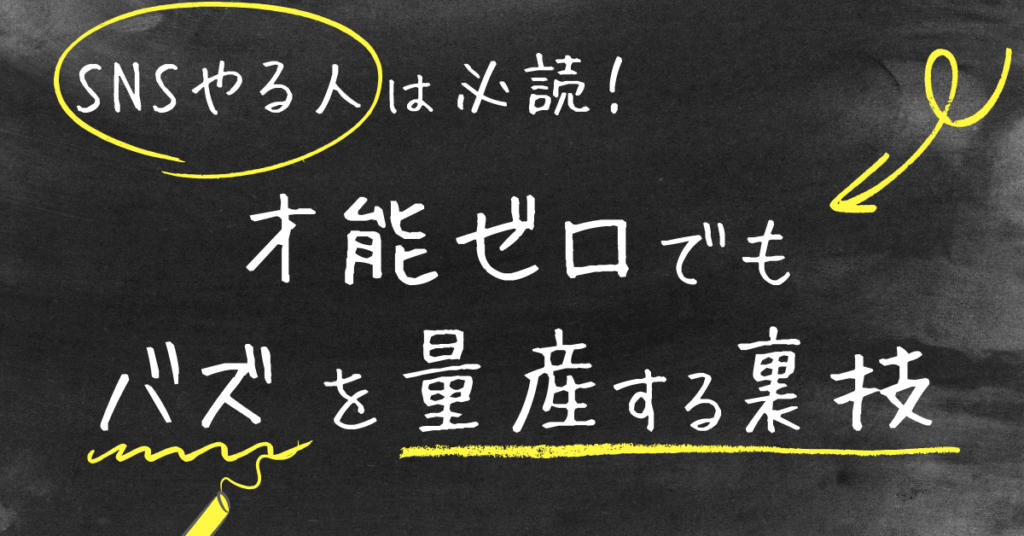生成AIの発展により、SEO対策は大きな転換点を迎えています。
従来の「キーワードを詰め込む」「大量の記事を作る」といった手法は通用しなくなり、AIに引用され、高評価を受けるコンテンツ作りが求められる時代になりました。
本記事では、LLMO(※1)やGEO(※2)といった新しいマーケティング概念を踏まえ、AI時代に評価されるコンテンツの特徴と具体的な作成方法を解説します。
- ※1:LLMO(Large Language Model Optimization)=大規模言語モデル(ChatGPTやGeminiなど)に最適化したコンテンツ戦略
- ※2:GEO(Generative Engine Optimization)=AI検索エンジン(Google AI OverviewやPerplexityなど)で上位表示されるための最適化手法
今コンテンツの質が重視される理由
AI時代にコンテンツの質が重視される背景には、検索エンジンを取り巻く3つの構造変化があります。
コンテンツ供給側の変化『AI生成記事の大量発生』
生成AIの登場により、誰でも短時間で大量の記事を作成できるようになりました。この技術革新は直近2年間で急速に進み、Web上には似たような内容の記事が溢れる状況になっています。
プラットフォーム側の対応『評価基準のシフト』
Googleをはじめとする検索プラットフォームは、アルゴリズムの評価軸を大きく変更しました。従来重視されていた「記事の本数」や「被リンク数」だけでなく、コンテンツそのものの信頼性・事実性・独自性が評価の中心になっています。
ユーザー行動の変化『質の高い情報への需要』
AI生成記事が増えた結果、ユーザーのリテラシーも向上しました。特にBtoB領域では「どうせAIで作った記事でしょ」という疑いの目で情報を見るユーザーが増えており、本当に役立つ独自性の高い情報が求められています。
このような三者の関係性の変化により、プラットフォームは独自性が高く、ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを優先的に表示するようになったのです。
Googleがコンテンツの独自性を判断する方法
独自性の高いコンテンツが重要だとわかっても、「Googleはどうやってそれを判断しているのか?」という疑問が残ります。
文字列解析による一次評価
Googleのクローラーは、記事内の特定の文言を認識できます。たとえば「自社で検証してみた」「独自調査の結果」といった文字列や、公式データからの引用を示す記述を読み取り、評価対象としていると考えられます。
画像認識技術の活用
文字情報だけでなく、ページ内の画像もレンダリング(※3)して認識しています。自社で撮影した写真、オリジナルの図表、検証結果のスクリーンショットなどがあれば、「このサイトは実際に検証している」と判断される可能性が高まります。
- ※3:レンダリング=Webページを実際にブラウザで表示した状態で解析すること
ユーザー行動データによる二次評価
一次評価で上位表示されたページは、その後のユーザー行動データによって再評価されます。滞在時間が長い、次のページへの遷移率が高い、直帰率が低いといった「良い行動」が確認されれば、さらに評価が高まる仕組みです。
実際、特定のキーワードで検索ニーズに合った費用相場や具体的な数値データを提供しているページが、AI Overviewに引用されやすいという検証結果も出ています。
AI時代に評価されるコンテンツ要素
AI検索エンジン(LLM)に評価され、引用されるコンテンツには、共通する5つの要素があります。
関連性『検索意図に的確に答えている』
ユーザーの検索クエリに対して、的確な答えが構造化されて提示されていることが重要です。FAQページや見出しが整理されているページは、AIにとって「分かりやすいページ」と判断されます。
権威性『専門家による監修・執筆』
記事の監修者や執筆者のプロフィールは、一定の重要性を持ちます。Web上で認知されていない専門家でも掲載すべきです。
たとえ広く認知されていなくても、プロフィール情報を掲載することで、ユーザーが記事を信頼しやすくなります。これは検索アルゴリズムの一次評価よりも、ユーザー行動による二次評価に影響するためです。
所属団体や役職、専門領域が明記されていれば、ユーザーは「この情報は信頼できる」と判断し、良好なエンゲージメント行動(滞在時間の増加など)を示します。
明確性『わかりやすい文章構成』
見出しで適切に構造化され、箇条書きや表を使って整理されている記事は評価されやすくなります。「一文で結論を示す」「専門用語には注釈を入れる」といった工夫も効果的です。
事実性『データに基づいた信頼できる情報』
AI時代で最も重視されるのが『事実性』です。「本当にその情報は正しいのか?」という観点で、以下のような要素が評価されます。
| 評価要素 | 具体例 |
| 一次データ | 自社で実施した調査やアンケート結果 |
| 検証結果 | 実際に商品・サービスを使った効果測定 |
| 公式データの引用 | 政府統計、企業の公式発表など信頼性の高い情報源 |
| 引用元の明記 | データの取得日時、出典URLの記載 |
エンゲージメント『読後のユーザー行動を促す設計』
記事を読んだ後、ユーザーがどのような行動をとるかも評価対象です。
- 潜在層向け記事:関連記事への内部リンクで回遊率を高める
- 顕在層向け記事:サービスページやお問い合わせへの導線を設置
- コンバージョン測定:サンクスページの実装でユーザーの成果を可視化
これらの設計により、「ユーザーにとって価値のある記事だった」とプラットフォームに認識されます。
一次情報を含んだコンテンツの型
事実性を担保するための「一次情報」には、大きく分けて4つのタイプがあります。
自社データ・アンケート結果
自社で設計した調査票を用いて実施したアンケートは、高い信頼性があります。
最近では、短期間・低コストでアンケートを実施できるSaaSツールが登場しています。1件あたり5万円前後でN数を確保した調査が可能です。
従来の記事制作費を削減し、その分をアンケート費用に充てることで、よりリッチなコンテンツを作成できます。
自社検証・実験結果
商品やサービスを実際に使用し、その効果を測定した結果は非常に価値があります。検証プロセスをスクリーンショットや動画で記録し、記事内に掲載することで信頼性が高まります。
取材・インタビュー
社外の専門家へのインタビューや、現場の生の声を届けるコンテンツも有効です。文字起こしだけでなく、動画も併せて掲載することで、さらに信頼性が向上します。
独自の視点・ノウハウ
担当者の業界経験やプロフェッショナルとしての知見も、独自性の高い情報として評価されます。専門家だからこそ語れる実践的なノウハウは、他の記事との差別化要素になります。
AI生成記事×一次情報のハイブリッド戦略
最もコストパフォーマンスの高い記事制作方法があります。具体的には、以下の3ステップです。
- AI生成ツールで記事の基本構成を作成(コスト:数十円〜数百円)
- 一次情報だけを手動で追加(自社データ、検証結果、アンケート、画像など)
- 公開後、ユーザー行動データを確認し、必要に応じてリライト
| 項目 | 従来の方法 | ハイブリッド戦略 |
| 記事制作費 | 8万〜10万円/本 | 数百円〜5万円/本 |
| 制作時間 | 数日〜1週間 | 数時間〜1日 |
| 独自性 | ライター次第 | 一次情報で担保 |
| AI評価 | 不明瞭 | 検証済みで高評価 |
この方法なら、記事制作費を大幅に削減しつつ、AI評価の高いコンテンツを量産できます。削減した予算をアンケート調査や検証活動に回すことで、さらにリッチなコンテンツ作りが可能です。
既存記事のリライトでも効果を発揮
新規記事だけでなく、既存記事にも同じ戦略が適用できます。リライトの手順としては、以下の4ステップです。
- SEOで一定順位にある記事を選定(5位〜20位程度)
- 一次情報を追加(自社データ、検証結果、専門家の見解など)
- 画像やビジュアル要素を強化(図表、スクリーンショット、動画)
- 公開後の順位変動を確認
実際、一次情報を追加するリライトを行うだけで、検索順位が大きく上昇したケースが複数確認されています。
SEOとAIに関するよくある質問
Q1:LLMO・GEO・AIOとは何?SEOとの違いは?
LLMOは大規模言語モデル(ChatGPTやGeminiなど)に最適化する戦略、GEOはAI検索エンジン(Google AI Overviewなど)での上位表示を目指す手法、AIOはAI全般への最適化を指します。
従来のSEOが「Googleの検索結果ページ」での順位向上を目的としていたのに対し、これらは「AIによる引用・参照」を重視する点が最大の違いです。
検索結果に表示されるだけでなく、AIが直接ユーザーに情報を提供する際の情報源として選ばれることを目指します。
Q2:AI生成記事でもSEOで上位表示できる?
AIで生成した記事でも上位表示することは可能です。ただし、AI生成記事をそのまま公開するのではなく、一次情報を追加することが不可欠です。
自社で実施したアンケート結果、検証データ、専門家の見解、オリジナルの図表などを組み合わせることで、AIで作った記事でも高評価を得られます。
実際の検証では、AI生成の基本構成に一次情報を加えるだけで、検索1位やAI Overviewへの引用を獲得した事例が複数報告されています。重要なのは「独自性」と「事実性」です。
Q3:専門家プロフィールは本当に必要?普通の人でも効果はある?
Web上で広く認知されていない専門家であっても、プロフィール情報を掲載すべきです。理由は2つあります。
1つ目は、ユーザーが「この情報は信頼できる」と判断し、滞在時間の増加や回遊率向上につながるため。
2つ目は、Googleがユーザー行動データを基に記事を再評価する「二次評価」において、良好なエンゲージメントが確認されると順位が上昇するためです。所属団体、役職、専門領域を明記することで、記事の権威性が大幅に向上します。
Q4:一次情報を集めるのに低予算でも実施できる?
低予算でも十分、一次情報を集めることは可能です。最近では、短期間・低コストでアンケートを実施できるSaaSツールが登場しており、1件あたり5万円前後でN数を確保した調査ができます。
また、自社で検証できるテーマ(商品の効果測定、ツールの比較実験など)であれば、ほぼコストゼロで一次情報を生成できます。
従来の記事制作費(8万〜10万円/本)を削減し、その分をアンケートや検証に充てることで、よりリッチなコンテンツを低予算で作成できる時代になっています。
Q5:記事をリライトする際、どの記事から手をつけるべき?
5位〜20位程度の記事から優先的にリライトすることをおすすめします。この順位帯の記事は、Googleから一定の評価を受けているものの、あと一歩で上位表示できる可能性が高いためです。
リライトの際は、一次情報(自社データ、検証結果、専門家の見解)を追加し、オリジナルの図表やスクリーンショット、動画などのビジュアル要素も強化しましょう。
実際、このリライト手法だけで検索順位が大幅に上昇したケースが多数報告されています。
まとめ:AI時代のSEO記事制作の新常識
生成AIの影響により、SEO対策は「量」から「質」へと完全にシフトしました。
重要なポイント
- 従来のSEO対策(内部対策・外部対策・コンテンツ対策)は引き続き必須
- その上で、AIエンジン全般に向けた最適化(LLMO・GEO・AIO)が必要
- 一次情報の活用がコンテンツの事実性を高め、AI評価を向上させる
- AI生成×一次情報のハイブリッド戦略が最もコストパフォーマンスが高い
今すぐできるアクションプラン
- 既存の上位記事に一次情報を追加するリライトを実施する
- 自社で検証可能なテーマを洗い出し、実験・調査を開始する
- 低コストで利用できるアンケートツールを導入する
- 記事内に専門家プロフィールや監修者情報を追加する
- 検証結果を画像・動画で可視化する仕組みを整える
AI時代においても、ユーザーに本当に役立つ独自性の高いコンテンツこそが最強のSEO対策です。生成AIを効率化ツールとして活用しながら、人間にしか作れない価値を提供していきましょう。